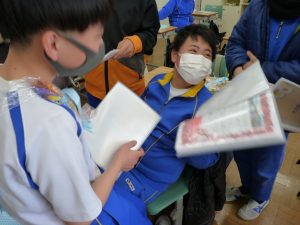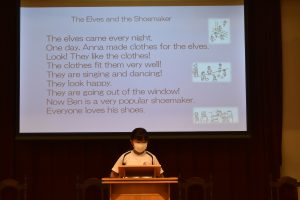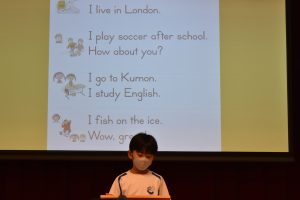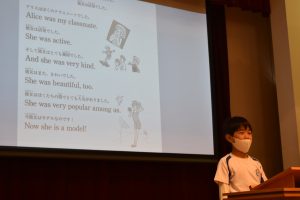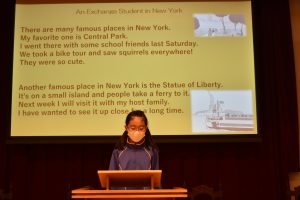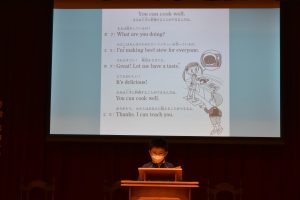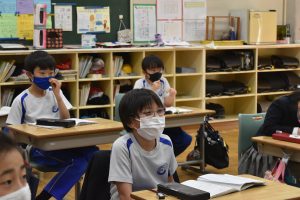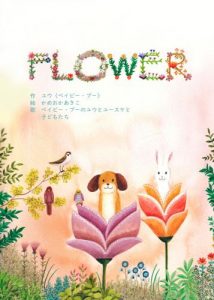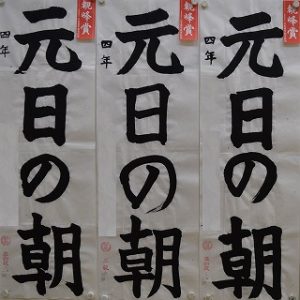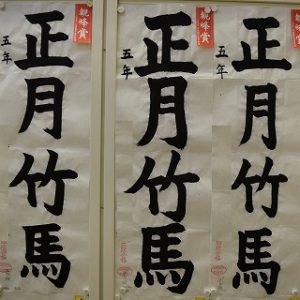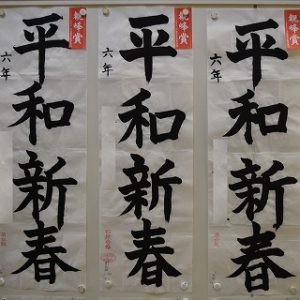今年度初旬に申請していたタブレット端末がようやく納入されました。文部科学省のGIGAスクール構想による整備事業でしたが、折しも新型コロナウイルス感染拡大のため全国の学校の多くがオンライン授業を行うことになり、申請が殺到したため納入時期が大幅に遅れることになりました。今年度、十分に利用してもらうことができず申し訳ないと思いますが、残りの時間できるだけ活用できればと思います。
7年前の学校通信にネット依存について、次のような引用文を掲載しました。
「厚生労働省研究班の調査でインターネット依存の疑いの強い中高生が推計で全国に52万人いるという結果が発表されました。この数は全国の中高生の実に8%ということです。研究班は、多くの若者がパソコンやスマートフォンなどで情報交換やゲームに没頭し、日常生活や健康に影響が出ていると指摘しています。調査の質問項目の中には、ネットを使う時間を短くしようとすると落ち込みやイライラを感じるか、熱中しすぎを隠すため、家族にうそをついたことがあるか、問題や絶望、不安から逃げるためにネットを使うといったものがありそんな傾向の強い生徒が多くいることになります。」 岡田尊司著 『脳内汚染からの脱出』 (文春新書、2007年)
この本は2007年出版の本ですが、それから14年経ち、情報社会はさらに発達し、それにともなうさまざまな問題が起こっています。インターネット依存の子どもの数は更に増えているでしょうし、低年齢化も進んでいると思います。
最近出版された「スマホ脳」という本の帯には次のような文が書かれています。
「1日4時間、若者の2割は7時間使うスマホだが、スティーブ・ジョブズを筆頭にIT業界のトップは我が子にデジタルデバイスを与えないと言う。なぜか?
睡眠障害、うつ、記憶力や集中力や学力低下、依存、最新研究が明らかにするのはスマホの便利さに溺れているうちにあなたの脳が確実に蝕まれていく現実だ」
アンディッシュ・ハンセン著 久山葉子訳 『スマホ脳』(新潮新書、2020年)
著者はデジタルデバイスを否定しているわけではなく、その使い方についての提言をしています。技術の発達によって以前では考えられないほど情報の発信や収集が容易になってきました。また、インターネットは便利で大きな可能性があり、世界中とつながることができますが、それを悪用する人もいます。自分自身や社会に及ぼす影響を十分に理解し、一人一人が意識して自分の身を守る心を育てていきたいと思います。ご家庭でもデジタルデバイスに触れる機会がありますので、その使い方にご留意いただければと思います。
さて、久しぶりの校外での学校行事、駅伝大会が行われました。整備されたトラックで思う存分走ることができました。応援してくださった保護者の皆様ありがとうございました。
駅伝大会のあと学校に戻り6年生を送別するお別れセレモニーでは、在校生から6年生へ感謝と、新たな中学校生活へのエールを送り、6年生が感謝と決心を述べました。毎年、この行事が終わるといよいよ卒業が目の前に迫ってきて、卒業を意識しはじめます。来週は卒業祈祷週がもたれ、6年生が小学校生活の中で経験したさまざまなことから証しします。この証しは後日、動画配信する予定です。
いよいよ3月になり、締めくくりの月となります。残り少ない日々を大切に過ごしていきたいと思います。
<学校通信 2020年度 第13号>